

誰にでも好きな色・嫌いな色はあると思いますが、色が持つパワーを知っている人は一部です。
色のパワーを取り入れることで、毎日の生活や仕事がもっとうまく行くかもしれません!
そんな色彩と心のプロがカラーセラピスト。カラーセラピストは幅広い分野で活躍中ですが、一体どのような資格が必要なのでしょうか?
実際のカラーセラピストの仕事内容も紹介します。
カラーセラピストは、色が心理に与える効果などを用いて心身の状態を良い方向へと導きます。
選んでもらった色から心の状態を読み取ったり、自己治癒力を活かしてアプローチしたりするのが主な仕事です。 色彩についての知識は様々な場面で応用できるため、最近ではカラーセラピストは様々な企業や分野などでも活躍しています。
カラーセラピストになるためには、色の持つ意味や及ぼす影響など基礎から実践的な内容までの知識が必要です。
カラーセラピストは国家資格ではないため、必須となる資格はありません。 独学でカラーセラピストになるのも可能です。 カラーセラピストになるためには、主に以下の様な内容について知識が必要です。カラーセラピーは特に若い女性から人気で、関連書籍が多数市販されています。
入門的なものから専門的な内容のものまで様々ですが、全ての知識を書籍から得るのは難しいでしょう。 日常に簡単に色の力を取り入れる程度であれば、書籍が適しています。 しかしカラーセラピストを目指すときは、より整理されたカリキュラムで学べる手段を選択するのが賢明です。カラーセラピーに関するスクールやセミナーは、近年特に人気が出てきています。
気軽に参加できる単発のコースもありますが、カラーセラピストになりたい方は、養成コースや時間をかけて学べるコースを選択しましょう。 スクールやセミナーなどでは、段階的に知識を整理しながら演習なども交えて学習できます。 生徒同士の交流を通して新たな発見もあるかもしれません。 週末に通うことで、仕事をしながらでも両立は可能です。 時間や場所の制約を受ける点や、費用がやや高めである点はデメリットだと言えます。最近はオンライン講座が充実しています。
カラーセラピーのオンライン講座も多数あるため、興味のあるものを受講してみるのも良いでしょう。 オンライン講座では、自宅から受講できて便利です。 近くに講義が受けられる環境がない場合にも良いですね。 ただし、オンライン講座は積極的に学ぶ姿勢がないと挫折してしまいがち。 価格が手ごろなため、ついサボってしまう気持ちもあるかもしれませんね。 また、オンライン講座は個人でも簡単に開講できるため質の差も目立ちます。 申込み前には口コミなどを確認した方が安心です。カラーセラピストの知識は、通信講座でも習得できます。
通信講座では資格取得が目指せるものも多いため、知識を証明できるものを探している人にもおすすめです。 通信講座は、学習する時間も場所も選びません。 毎日の生活に無理なく組み込めて継続しやすいのです。 試験対策ができるもの、資格取得が保証されているもの、受験資格が必要なものなど様々なものがあるため、必ず事前に確認しましょう。 通信講座は、初心者でも資格取得まで進めるカリキュラムが確立されています。 今の生活を大きく変えずにカラーセラピストになるには、最適です。
私たちの生活と色は切っても切れない関係にあります。
そのため、カラーセラピストの仕事の範囲は多岐にわたっているのです。 具体的にはどのような分野でカラーセラピストが活躍しているのでしょうか? その仕事内容も併せて見てみましょう!ファッション業界は、色の影響を大きく受けます。
毎年流行色がありますが、その色が心理に与える影響が分かっていると販売戦略も立てやすいでしょう。 アパレルメーカーでも活用場面が多く、店舗の仕入れやディスプレイなどにも応用できます。 またお客様とのコミュニケーションの中から、希望に合わせた色選びをしてあげられるかもしれません。 オンラインでの販売時に色の効果を用いるのも良いでしょう。 ファッションに関係する分野では、カラーセラピストの知識が活用できる部分が多いですね!デザインと色とはもちろん密接な関係にあります。
どのような印象を与えたいのかによって使うべき色が分かるため、カラーセラピストの知識はかなり役立つはずです。 特に広告のデザインなどは印象が大事。 ターゲットにうまく届く広告にするには、色のインパクトが必要なのです。 色彩の効果をよく知るカラーセラピストならではの提案が出来ることによって、デザイン業界で活躍できるでしょう。カラーセラピーの診断を、個人のサロンなどで行うのも人気があります。
自分について、自分がすべて把握しているとは限りません。 深層心理なども考えると、自分でも分からない部分の方が多いのです。 カラーセラピーの診断を通して、自分が気づいていない深層心理に気が付きます。 さらに色の力を活かす方法が習得できると、得るものは大きいでしょう。 サロンでの診断はSNSや口コミなどで募集するのも可能なため、低予算で宣伝ができます。 カラーセラピストだけで生活をするのは難しいかもしれませんが、副業としてサロン診断を行っている人は多いです。 直接相談者の笑顔が見られるため、カラーセラピストとしてのやりがいを感じる仕事と言えます。カラーセラピストとしての知識は、企業や個人のイメージアップにも活用できます。
マナーや心理系の知識と併せて新人研修を行ったり、営業職のための講義をするのも可能です。 カラーセラピストとして契約するのは難しいかもしれませんが、他の資格や知識を併用出来るとカラーセラピストは強みになります。 サロンなどで診断の経験が積まれていると、そこから仕事につながる場合もあるかもしれませんね。カラーセラピストは、色彩を用いた環境作りが得意です。
福祉施設ではよりリラックスできるような空間作りが必要で、教育機関では集中とリラックスのバランスも必要でしょう。 カラーセラピストの知識を活かして壁紙やインテリアなどの色を選定し、目的に合った空間が作れます。 福祉施設や教育機関でもカラーセラピストは活躍できるのです。
カラーセラピストに関心がある人は多いでしょうが、実際に自分が向いているのかどうか分からないのではないでしょうか?
そこで、カラーセラピストに向いている人と向いていない人をまとめました。 参考にしてみてください。カラーセラピストは、単に相談者が選んだ色だけを情報に診断をする訳ではありません。
それを選んだときの様子や色を見たときの反応など、様々な要素が診断の材料になるのです。 観察をするのは、セラピストとして大事な仕事。 それが苦手な人は、カラーセラピストには向いていません。 趣味で自分の生活にカラーセラピストの知識を活かす程度に限られるのであれば、人に伝えるのが苦手でも大丈夫でしょう。 しかし、誰かの診断をしたりする場合には伝える技術ももちろん必要になります。 練習を重ね、コツをつかむことで上達するものですが、やはり苦手な場合は努力が必要です。 自分の体調によって、色の感じ方が異なる経験はないでしょうか。 気分が安定しなかったり体調が安定しなかったりする人は、他人の診断をするのは困難です。 まずは自分自身が心身共に安定できる方法を身につけましょう。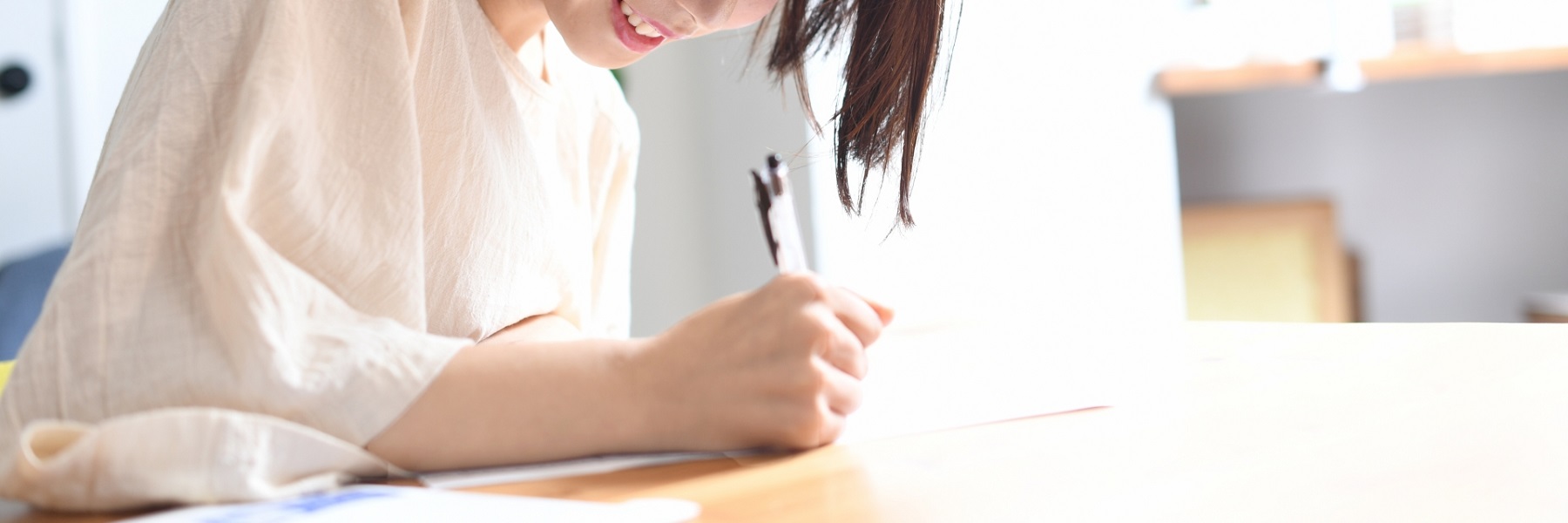
カラーセラピストになるためには、色の働きや効果などから色による演出方法まで、幅広い知識が必要です。
カラーセラピストとして活動する上で必須の資格はなくても、やはり資格があると信頼度は大きく変わります。 資格取得への道のりが結果的にはカラーセラピストに必須の知識の確認にもなるため、何らかの資格は取得していた方が良いでしょう。 カラーセラピストに役立つ資格としては、以下の様なものがあります。カラーセラピスト®は、日本色彩環境福祉協会が認定する民間資格です。
色彩交流カード・色彩コラージュなどを用いて、相談者の心を解放し癒すための知識や技術を習得している人に資格が与えられます。 通信講座または通学講座を受講し、修了後の試験に合格するとカラーセラピスト®としての認定が受けられます。 『色彩福祉士資格』を併せて取得することによって、資格取得のための教室を開くのも可能です。 在宅受験で、60%以上の評価があれば合格とされます。カラーセラピスト資格は、日本能力開発推進協会 (JADP)が認定する民間資格です。
色を手段として相談者の心理状態を読み取り、カウンセリングによって解決へと導くための知識と技術を習得している証明となります。 協会指定の認定教育機関等が行う教育訓練を受け、その全カリキュラムを修了すると受験資格が得られます。 カリキュラムは、通信講座で受講可能です。 試験は在宅でいつでも受験OK。 好きなタイミングで受講できるのはうれしいですね。 70%以上の評価で資格取得できます。カラーセラピーは、日本メディカル心理セラピー協会(JAAMP)が認定する民間資格です。
カラーセラピーは色彩療法とも呼ばれ、古い歴史を持っています。 色の持つ意味、色に対する捉え方の違いなどを利用して心理に働きかけることによって、心理状態を改善できるのです。 カラーセラピーには受験資格はありません。 在宅受験で、偶数月に行われる資格試験に合格すると認定が受けられます。 合格するには、70%以上の評価が必要です。
カラーセラピストになるには、カラーセラピーの基礎や応用を十分に身につけなければなりません。
それには資格があった方が◎。 複数の資格があれば印象も異なるため、できることなら複数取得を目指しましょう。 特におすすめしたいのはこの資格です!カラーセラピーは受験資格が設けられておらず、通信講座で学べるため、どこに住んでいるどんな状況の人でも資格取得が可能です。
基礎から実践的な内容まで幅広く問われる試験で、取得してからは知識と技術の証明になります。 通信講座の中には、カラーセラピーと他の関連資格を同時に取得できるものもあります。 知識の拡大や証明が可能で、仕事にする際に大きな強みになるでしょう!カラーセラピー資格を取得するには、以下の2つの通信講座がおすすめです。
カラーセラピー3資格取得講座は、諒(りょう)設計アーキテクトラーニングの通信講座です。
この講座では、『カラーセラピー』『色彩インストラクター』『カラーアドバイザー』の3資格同時取得が目指せる内容です。 1つの講座で3つの資格取得が目指せるのは、かなりお得と言えるでしょう。 3資格だから大変だと思うかもしれませんが、カラーセラピー3資格取得講座の学習は1日たったの30分でもOK! コツコツ続けると、約半年でカリキュラムを終えられます。 最短ならば約2か月での資格取得が目指せるため、今すぐ知識を身につけたい人にもおすすめですよ! さらに驚きなのが、スペシャル講座のお得さ! スペシャル講座は通常の講座+20,000円(税込)ですが、なんと資格保証が付いていて卒業と同時に3つの資格が取得できてしまうのです。 条件は、卒業課題1回の提のみ。 通常ならば、カリキュラム修了後に3つそれぞれの資格試験に申し込まなければならないのですが、スペシャル講座はそれもなく簡単です。 資格試験は、1つにつき10,000円(税込)。スペシャル講座は楽な上に、結果的には10,000円お得になってしまいます! やっぱりお得過ぎますね。| カラーセラピー3資格取得講座 | ||
| 通常の講座 | 試験対策 添削課題5回 | 受講料:59,800円(税込) |
| スペシャル講座 | 資格保証付 添削課題5回+卒業課題1回 | 受講料:79,800円(税込) |
カラーセラピー講座は、SARAスクールの通信講座です。
カラーセラピー講座では、カラーセラピーの人気資格である『カラーセラピー資格』『カラーアドバイザー資格』『色彩インストラクター資格』の3つの資格取得が目指せます。 SARAスクールは毎日を頑張る女性に人気の講座が多数。 カラーセラピー講座はその中でも実用性が高いと人気です。 カラーセラピー講座は、毎日30分程度の学習で約6か月で資格取得まで進めます。 1日に30分なら、何かの待ち時間や寝る前のちょっとした時間でも確保できますよね。 現実的に可能なカリキュラムになっている点がうれしいです。 3資格もあると、勉強量もかなりのものだと想像してしまうでしょう。 実はこの3つの資格は共通する部分も多く、カリキュラム通りに進めると効率良く学習ができるのです。 最短2か月でカリキュラム修了も可能なのが、その証拠でしょう。 カラーセラピー講座で特におすすめが、資格保証付のプラチナコース! 価格が少し高いため躊躇してしまうかもしれませんが、実は試験の受験料が1つ10,000円(税込)かかるためプラチナコースの方がお得。 しかも試験が免除になるのであれば、プラチナコースを選ばない理由がありません。 プラチナコースは、通常の添削課題5回+卒業課題1回の提出のみで『カラーセラピー資格』『カラーアドバイザー資格』『色彩インストラクター資格』の3資格が確実に取得できます。 カラーセラピストへの近道ですね!| カラーセラピー講座 | ||
| 基本コース | 試験対策 添削課題5回 | 受講料:59,800円(税込) |
| プラチナコース | 資格保証付 添削課題5回+卒業課題1回 | 受講料:79,800円(税込) |
